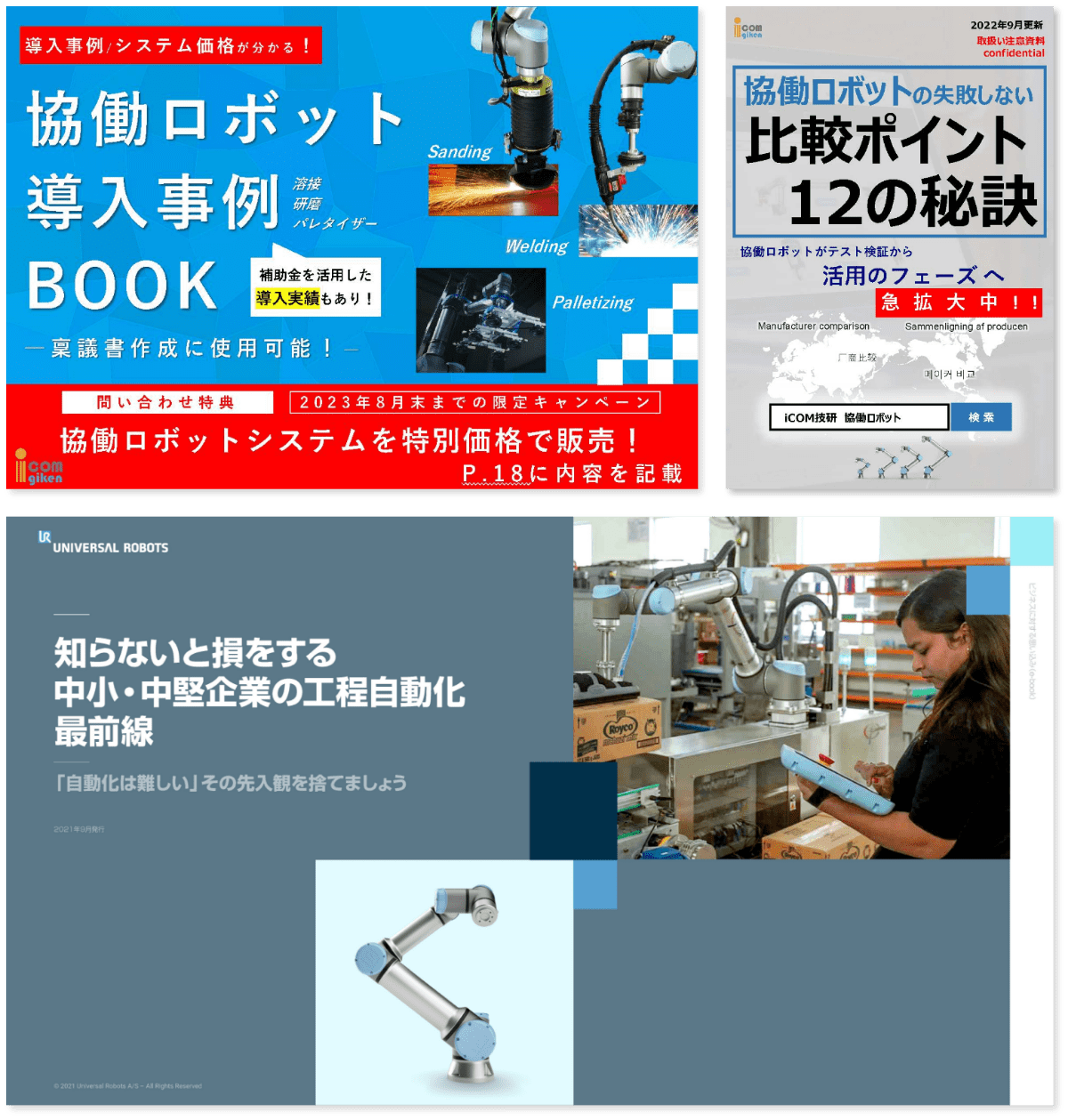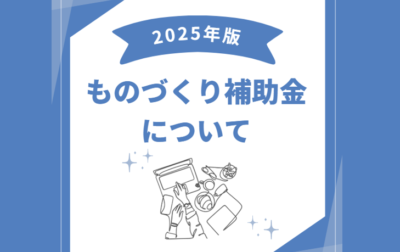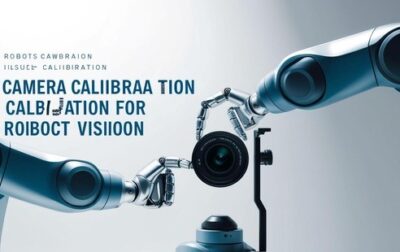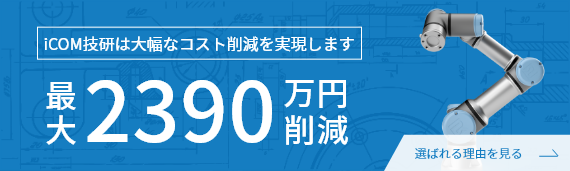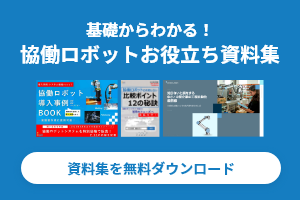国内の製造業、特に中小規模の工場では、「仕事はあるのに人がいない」という課題「人材確保」が深刻化しています。
団塊世代の引退、若年層の製造離れ、少子高齢化といった構造的要因により、人材確保が困難になっているのが現状です。
このままでは「受注があるのに製造できない」――そんな危機感を抱える企業も少なくありません。
人材不足時代の製造業に求められる「人材確保」の一手について、協働ロボットSIerとして掘り下げて考えてみました。
目次[]
海外出身の仲間と共に現場を支える

多くの製造業が海外から来日した技能人材との協働に取り組んでいます。
ベトナムやインドネシア、フィリピンなどの国々から来日した若者たちは、現場での実習や技術研修を通じて、徐々に力をつけ、日本人スタッフと共に生産現場を支えています。
中には、長年日本で経験を積み、工場長や品質管理の責任者として現場の中核を担う方もいます。
参考:育成費に100万円、元技能実習生は工場長に昇進 三栄金属製作所 | 日経クロステック(xTECH)
企業側も、言語や文化の違いを尊重しながら、以下のようなサポート体制を整えています:
- 日本語教育の実施
- 職場でのコミュニケーション支援
- 技術習得や資格取得に向けた研修制度
こうした取り組みによって、多様な背景を持つ人材が安心して働ける環境が生まれつつあります。
協働ロボットで「人材確保」の選択肢

一方で、協働ロボットを導入する企業も増えています。
従来のロボットとは異なり、協働ロボットは人と同じ空間で安全に作業できるため、スペースに限りがある工場でも導入が進みやすいのが特徴です。
単純で反復的な作業や、肉体的な負担が大きい工程をロボットに任せることで、次のような変化が生まれています:
- 作業の負担軽減とミスの減少
- 人が改善や判断業務に集中できる
- 工程の標準化と教育工数の削減
- 作業データの蓄積と可視化による現場改善
ロボットは「人の代わり」ではなく、人がより安全に、より活躍できる環境をつくるパートナーなのです。
共に働く人とロボット、それぞれの役割
人材不足が深刻化する製造業において、しばしば話題になるのが「外国人技能者を採用するべきか、それともロボットを導入するべきか」という議論です。
しかし、実際の現場ではこの二者択一の問いはあまりに単純すぎると言えます。
実情はむしろ、「人」と「ロボット」は明確に異なる強みを持ち、それぞれが補い合うように機能するというケースが増えています。
この“相互補完”の関係こそが、これからの現場にとって重要なキーワードです。
人の強み:判断力・応用力・多様性への対応
海外から来日し、技術を身につけた技能者たちは、作業の効率化やミスの削減といった生産面はもちろん、現場の雰囲気や文化に新しい風を吹き込む存在にもなっています。
また、経験を積んだ人材が持つのは、単なる作業手順の習得にとどまらない「現場で考え、工夫し、適応する力」です。
- 材料の微細な変化を感覚的に捉える
- 品質の異常を即座に検知し、現場で判断
- トラブルにも現場判断で柔軟に対応
このように、現場における「変化」や「例外」への対応力こそ、人の強みと言えるでしょう。
ロボットの強み:反復性・安定性・客観的な再現性
一方、協働ロボットは繰り返し精度が求められる単純作業や、物理的な負担が大きい工程において非常に高いパフォーマンスを発揮します。
- ネジ締めやピッキングなどの定型作業を長時間安定して実行
- 作業にバラつきが出ないため、品質も安定
- 残業・夜勤・繁忙期など、人手の確保が難しい時間帯でも稼働可能
さらに、ロボットの動作や稼働ログはデジタルで記録されるため、作業工程が自動的に「見える化」され、再現性や工程改善の起点にもなるという利点があります。
これからの人材確保に求められる“両輪の戦略”
これからの製造業に必要なのは、「人の力を最大限に活かしつつ、技術の力で支える」という考え方です。
- 多様な人材が安心して働ける職場を整える
- 作業環境や生産体制をロボットで支え、継続性と再現性を高める
- 人とロボットの協働によって、ノウハウが企業に蓄積され、次世代へと継承する
- 自動化のノウハウを企業の価値にする
これらを同時に実現することが、これからの工場の強みとなっていきます。
まとめ:人と技術の融合で人材確保を行い、未来のものづくりへ
現場の未来を考えるうえで、「人を増やすか、ロボットを入れるか」という単純な問いではなく、“人が活きる仕組み”をどう整えるかという視点が重要です。
海外から来た仲間とともに働き、協働ロボットと役割を分担しながら、よりよい製造現場を築いていく。
そんな姿勢こそが、今後の日本のものづくりを支える土台となっていくのではないでしょうか。