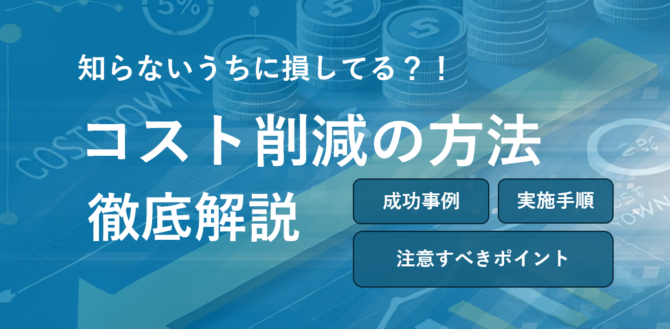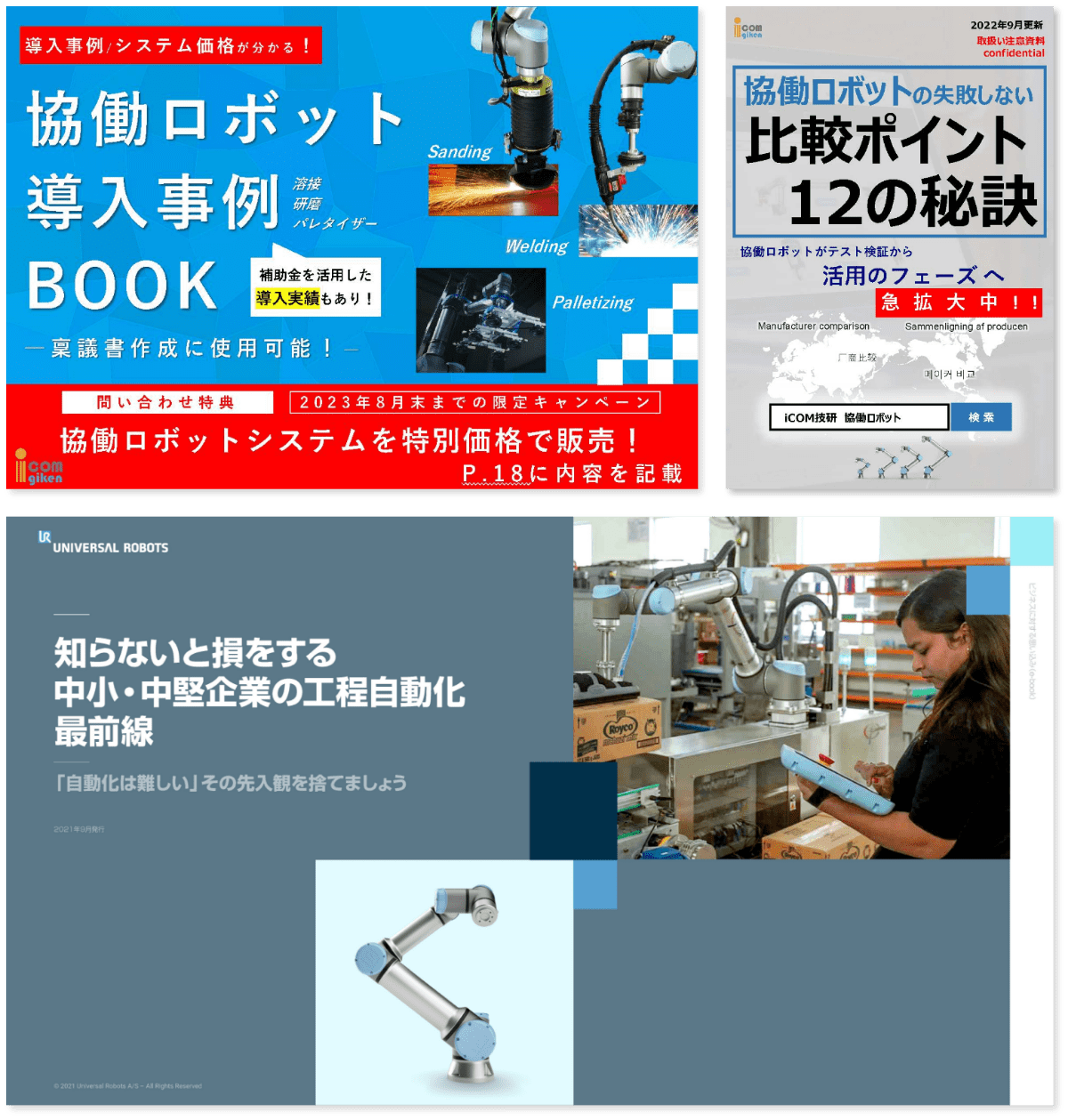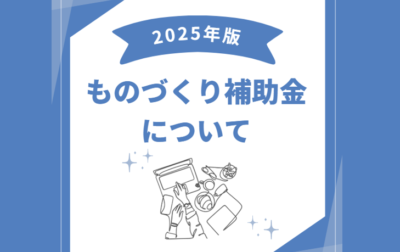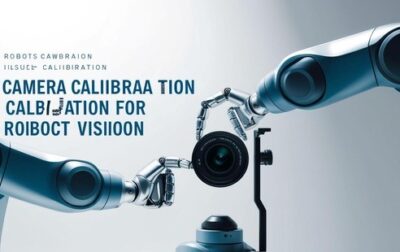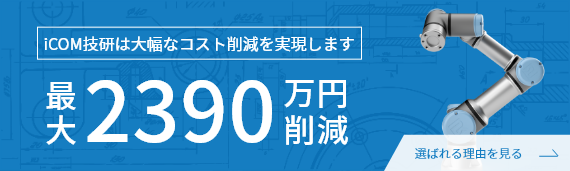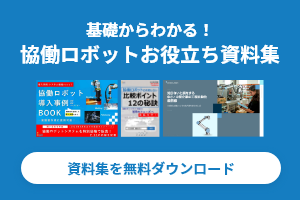製造業において「コスト削減」は重要な課題です。しかし、材料費や労務費、水道光熱費など、あらゆるコストが積み重なり、利益を圧迫します。特に近年は、エネルギー価格の高騰や人件費の増加が進んでおり、競争力維持のために対策が求められます。
とはいえ、単にコストを削減するだけでは不十分です。たとえば、人員を減らしたり、品質を落としたりすると、製品のクオリティ低下や納期遅延を招きかねません。その結果、企業の信頼を損なうリスクもあります。
そこで、本記事では製造業のコスト削減の基本を解説します。加えて、ムダを減らしつつ生産性を向上させる具体的な方法も紹介します。

経費計算シート
簡単に経費計算できるシートを作成しましたので、自社のコスト削減にぜひご活用ください!
目次[]
製造業におけるコスト削減の目的は?

製造業では、原材料の仕入れや、人件費などさまざまなコストが発生します。コスト削減に取り組む目的は、無駄なコストを減らし、生産性の向上や事業経営の安定化を図ることにあります。特に製造業は、世界情勢や環境問題の影響により、エネルギーや資材の高騰が上昇する可能性があるため、常にコスト削減に取り組むことは重要です。
- 生産性の向上
- 経営の安定化
- その他(研究開発の強化、DX化による企業体質の変革)
ただし、市場動向や自社の事業内容を無視して、盲目的にコスト削減を行うと、製品のクオリティ低下や納期遅延を招くおそれがあります。また、製造業のコスト削減を成功させるには以下の点を意識することが必要です。それは、QCD(コスト・品質・納期)の3要素のバランスを見ながら改善活動に取り組むことが大切です。
製造業におけるコストの種類は大きく分けて2種類?

製造業におけるコストは、大きく分けると製造原価と販売費及び一般管理費(以下、販管費)の2種類です。これらは、製造原価が製品を作
<製造原価>
以下の3種類であり、製品との関連性によって直接・間接の別があります。
- 材料費(製品製造に関わる材料や部品)
- 労務費(製品製造に関わる従業員の賃金)
- 経費(工場の賃貸料、減価償却費、水道光熱費、外注加工費など)
<販売費及び一般管理費>
製品の製造工程に直接関わらない分野の費用です。
役員報酬、賃金、福利厚生費、広告宣伝費、旅費交通費、通信費、研究開発費、賃貸料、水道光熱費、減価償却費、事務用品費、消耗品費、租税公課など
販売費には、商品を販売する営業スタッフの給与や交通費、商品の発送に必要な配送料、インターネット広告の出稿費などが含まれます。一方、一般管理費には企業の賃貸料や水道光熱費、経理スタッフの給料など、商品・サービスの販売とは直接的に関わらない費用が含まれることが特徴です。
製造業で削減しやすい費用は?
製造業においてコストを削減しやすい費用項目には、労務費、水道光熱費、通信費、移動費などが挙げられます。ただしコスト削減に取り組んでも、今日明日で効果が表れるわけではありません。また、費用の種類によってコスト削減の難易度は変わります。
製造にかかわる、材料費や外注費、燃料費は削減しにくいとされています。

一般的なコスト削減の例
たとえば、工具の配置を見直し、頻繁に使用するドライバーやレンチを作業台の手元に配置するようにします。すると、これまで作業のたびに工具を探していた時間が短縮され、スムーズに作業できるようになりました。
工具を取るのに要していた時間が、1回につき3秒縮まるとどうなるでしょうか。
従来の作業では、この部品を組み付ける作業のペースが、1時間に80個だったとします。
80個を組み付けるのに要する時間を3分短縮
(3秒×800個=240秒)1日8時間の作業に換算すると、
24分短縮(240秒×8時間=1920秒=32分)1か月の労働日数(20日)に換算すると、
38,400秒(640分 = 10時間40分) の短縮
80個を組み付けるのに要する時間を3分短縮(3秒×800個=240秒)
1日8時間の作業に換算すると、24分短縮(240秒×8時間=1920秒=32分)
1か月の労働日数(20日)に換算すると、38,400秒(640分 = 10時間40分) の短縮
ものづくり現場における3つ目のコスト削減とは?

製造に関わるコストの削減は、いずれの企業でも重要な課題です。コスト削減の方法として、もう一つ有効な手段があります。
1つは、材料費・光熱費・人件費など製造にかかる経費を圧縮し、切り詰めていく方法。もう1つは、ムダを無くす事で作業効率を向上させ、製造経費を削減する方法です。
前者は経営者を含めて検討する必要があるのに対し、後者は現場主導で進められます。作業者がコストを意識し、作業内容を見直すことも重要です。作業のムダを見つけて改善することで、業務の負担と経費を同時に減らす、前向きなコスト削減が実現できます。
前向きなコスト削減を行わないとどうなるのか
1. 人件費のコスト
年間の給与+福利厚生費+社会保険料など
月給 25万円 × 12か月 = 300万円
賞与 2か月分 = 50万円
社会保険・福利厚生(給与の15%と仮定)= 約52.5万円
合計人件費: 約402.5万円
2. 採用コスト
新しい人を採用するためのコスト(求人広告、エージェント手数料、面接・研修コストなど)
求人広告費 = 50万円
人材紹介手数料(年収の30%) = 120万円
面接・選考の工数(人事や現場の工数換算) = 10万円
研修コスト(入社後の教育費) = 30万円
合計採用コスト: 約210万円
✅ 人件費(給与+賞与+社会保険)→ 約400万円
✅ 採用コスト(求人・面接・研修など)→ 約200万円
➡ 合計 約600万円のマイナス!
特に専門職や管理職なら、さらにコスト増大!
早期退職を防ぐ対策が重要!

経費計算シート
簡単に経費計算できるシートを作成しましたので、自社のコスト削減にぜひご活用ください!
従来の費用対効果の計算方式
一般的な製造原価と販管費(販売管理費)の比率は、業界や企業のビジネスモデルによって異なりますが、一般的な目安は以下の通りです。
製造業の場合
- 製造原価(売上原価):売上高の 60~80%
- 販管費:売上高の 10~30%

A社は、自動化設備を導入しようとするも製造原価だけで費用対効果を計算していた。そのため、自動化設備を導入するための費用対効果が出せなかった。
自動化設備の導入を進めていた競合他社に値差をつけられ赤字化が進んだ。
正しい費用対効果の計算方式

近年は転職が増え、人材の流動性が高まり、安定した労働力の確保が難しくなっている。そのため、単に製造原価の削減だけを考えるのではなく、採用・教育コストや管理負担などの販管費も含めた総合的な視点で自動化設備の費用対効果を評価することが重要だ。


経費計算シート
簡単に経費計算できるシートを作成しましたので、自社のコスト削減にぜひご活用ください!
高い費用対効果を発揮する自動化設備とは
協働ロボットは、自動化設備の中でも特に高い費用対効果を発揮します。
その理由は、省スペースで設置でき、扱いやすい点にあります。さらに、人と同じ作業空間で稼働できるため、大がかりな安全柵を設ける必要がなく、導入コストを抑えやすいのも特徴です。
また、協働ロボットは、作業者が負担を感じる工程をピンポイントで自動化できます。たとえば、単純作業の繰り返しや、重い部品の持ち上げといった負担の大きい作業をロボットに任せることで、作業効率の向上と労働環境の改善が同時に実現できます。その結果、無理のない自動化が可能となり、人件費やそれに係る採用コストを削減することができます。
前向きなコスト削減の例(協働ロボット)
製造現場では、本来はやらなくて良い手順が含まれていたり、しんどい体勢での作業があり、通常より時間をかけてしまっていることがあります。
(例)現在、3kgの段ボールをパレットに積み付ける作業は手作業で行われています。しかし、この作業には以下のような課題が発生しています。
- 人材確保の問題
作業員の離職率が高く、新たな採用のたびにコストが発生している。- 作業負担と健康リスク
1日4時間の作業とはいえ、腰への負担が大きく、長期的な健康リスクがある。- 作業のミス
積み付け方のミスや、個数の誤りが発生しやすく、品質や作業効率に影響を及ぼしている。この問題を解決するために、自動化の導入が必要と考えます。適切な自動化技術を活用することで、作業の安定化、コスト削減、品質向上を実現できる可能性があります。今後、これらの問題を解決するための前向きなコスト削減を進めるべきではないでしょうか?
コスト削減の流れ

コスト分析
まず、現状のコストを正確に把握することが重要です。製造業の原価は「材料費」「労務費」「経費」に分けられ、それぞれの費用がどの程度かかっているのかを計算します。原価計算を行うことで、削減の優先度が明確になります。
コスト削減方法の策定
削減すべきターゲットが分かったら、効果の高い方法を選定します。すべてに手をつけるより、優先度の高い部分から取り組むのが効果的です。
- 経費の削減:電気料金の見直しが有効で、LED照明の導入やインバーター方式の採用が効果的です。
- 材料費の削減:在庫管理を改善し、仕入れの無駄を減らします。
- 労務費の削減:生産効率を向上させ、作業時間を短縮します。
コスト削減の実施
決定した改善策を実施し、どの程度の効果があったかを検証します。その結果をもとに、方向性の見直しやさらなる改善を行い、継続的にコスト削減を進めます。