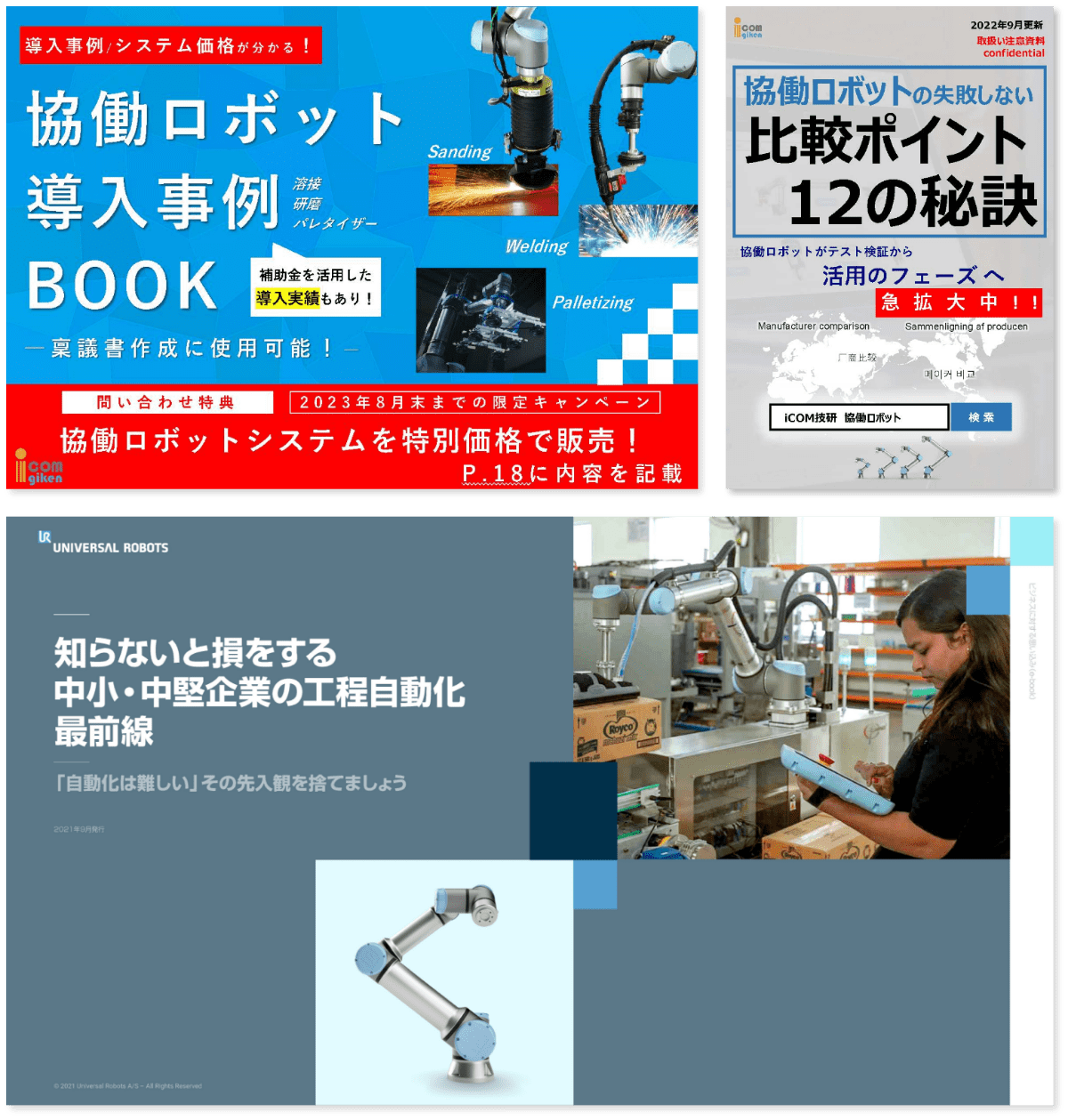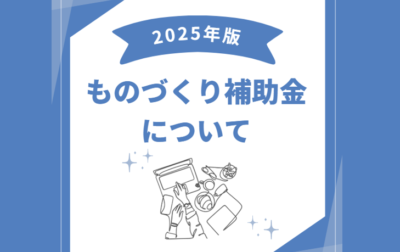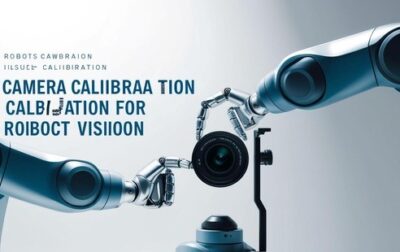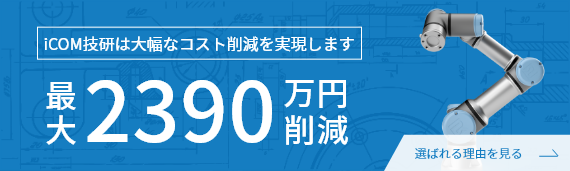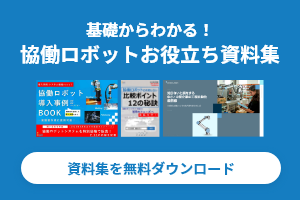近年の少子高齢化に伴い、様々なものづくりの現場で職人不足が問題となってきています。人材が安定しない、技術の伝承ができていないなど様々な現場の声をよく耳にします。今まで職人が行っていた研磨の自動化しようとお考えの方も多いと思います。
ロボットで品質を保てるの?や、そもそもロボットで研磨できるの?と思っている方も多くいると思います。
今回は、研磨の自動化の現状を皆様にお伝えしていきます。
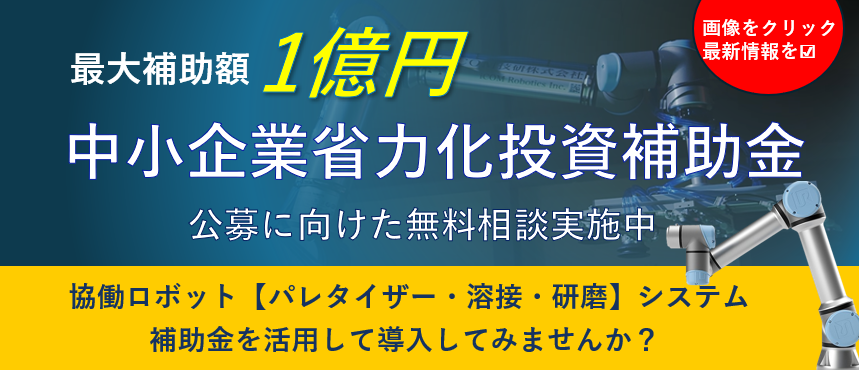
目次[]
研磨作業の抱える問題点

まず、人の手で研磨を行う問題点をいくつか挙げていきます。
人手不足・人材不足
研磨作業は専門的な技術や経験を必要とするため、熟練した作業員の確保が難しくなっています。特に高齢化や若年層の製造業離れにより、人材の確保が課題です。
作業の疲労・負担
研磨作業は長時間にわたる単調な作業や振動・騒音を伴うため、身体的な疲労や健康リスクが高いです。特に手作業の場合、手首や肩への負担が大きく、職業病のリスクも増します。
長時間の研磨によって、白蝋病といった振動障害になる事例も多くあります。

品質のばらつき
人による手作業では、作業員の熟練度や体調により品質のばらつきが生じることがあります。安定した高品質な仕上がりを維持するのが難しいという課題があります。
作業効率の低さ
手作業による研磨は自動化された機械に比べて時間がかかり、生産効率が低いです。また、作業時間が長引くと労働コストも増加します。
安全性の問題

研磨作業では、キックバックや金属粉や研磨剤の飛散、機械の振動・ノイズなどが作業者の健康や安全を脅かすことがあります。防護具を適切に使用しない場合、事故や健康被害のリスクが高まります。
熟練者の技術伝承の難しさ
熟練した作業者の引退などによって技術が失われるリスクがあります。技術の標準化やマニュアル化が難しく、次世代への技術継承が課題です。
なぜ研磨の自動化は難しいのか?

・形状と位置の変動
部品の形状や大きさが異なる場合、ロボットに適応させるのが難しいです。特に自由曲面や複雑な形状を持つ部品の研磨には、精密なパス計画が必要です。
・材料特性の変化
研磨する材料の硬さや表面状態によって、適切な研磨力やスピードを調整しなければなりません。異なる材料に対して柔軟に対応することが求められます。
・力制御の難しさ
研磨作業では一定の力で押し付けることが重要です。力制御が不十分だと、過剰な力で研磨してしまい表面を傷つけたり、逆に十分な研磨ができなかったりします。
・粉塵や環境の影響
研磨時に発生する粉塵がロボットやセンサーに影響を与える可能性があります。粉塵がセンサーを覆うと精度が低下し、ロボットの動作に支障をきたします。
・自動化の調整が難しい
自動研磨のプロセス設定には時間と労力がかかります。理想的な結果を得るためには、プログラムや力加減の微調整を行う必要があります。
研磨作業の自動化は無理?自動化は諦めた方が良い?
研磨作業の自動化はできます!!
近年、協働ロボットを用いて研磨作業の自動化が飛躍的に増えてきています。
もちろん、手研磨・自動化の両方の課題を解決します。
研磨自動化の最適な答えは?
なぜ協働ロボットが研磨作業の自動化に向いているのか?
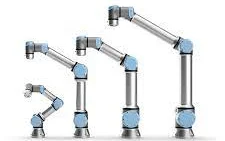
まず協働ロボットってなに?
協働ロボットは、人と一緒に作業ができる産業用ロボットです。産業用ロボットには安全柵を設置する義務がありますが、協働ロボットは義務づけられていません。そのほかにもいくつか特徴があります。
協働ロボット研磨の品質
高い品質を確保できる
従来、研磨の自動化が難しいとされてきた理由として、一定加圧ができないという問題がありました。
ファーロボティクスやATIのユニットにより人間と同じように加圧することができる力制御ユニットが登場したことによりその問題は解決されました。また、協働ロボットは±0.02mmと高い精度があります。
長時間の研磨作業でも品質が安定している
協働ロボットによる研磨は、長時間稼働させても高い品質を確保することができます。協働ロボットは、研磨作業をしているときに人が近くで品質確認を行う事もできます。
多品種の研磨自動化に対応できるのは協働ロボットだけ
協働ロボットは、多品種に対応できる唯一のロボットです。もちろん、お金をかければそれ以外のロボットでも多品種対応可能なのですが、、
主に2つの観点から協働ロボットの扱いやすさについて説明していきます。
柔軟に教示作業を行える
協働ロボットの大きな特徴として、教示作業の柔軟性が挙げられます。その一つとして、ロボットの先端を教示者が手で動かし座標を設定できます。(ダイレクトティーチング)また、弊社の提供するソフトウェアにより、他社のシステムに比べはるかに簡単な教示が実現できます。
教示作業を短時間で
扱いが簡単であるため、担当者が変わってもすぐに対応できます。また、弊社では、ロボットの教示方法を教えるロボットスクールの運営も行っています。
そのため、教示作業を外注に頼らず、自社の人材で協働ロボットを運用することができるのも魅力の一つです。
合わせて読みたい
お問い合わせ・無料研磨テスト依頼
カタログがご入用のお客様は、カタログダウンロードよりダウンロードしてください。
デモ依頼・お問い合わせお客様は、お問い合わせフォームよりお問い合わせください。
下記よりお気軽にご依頼ください、日時については弊社担当者からご連絡の上、調整いたします。